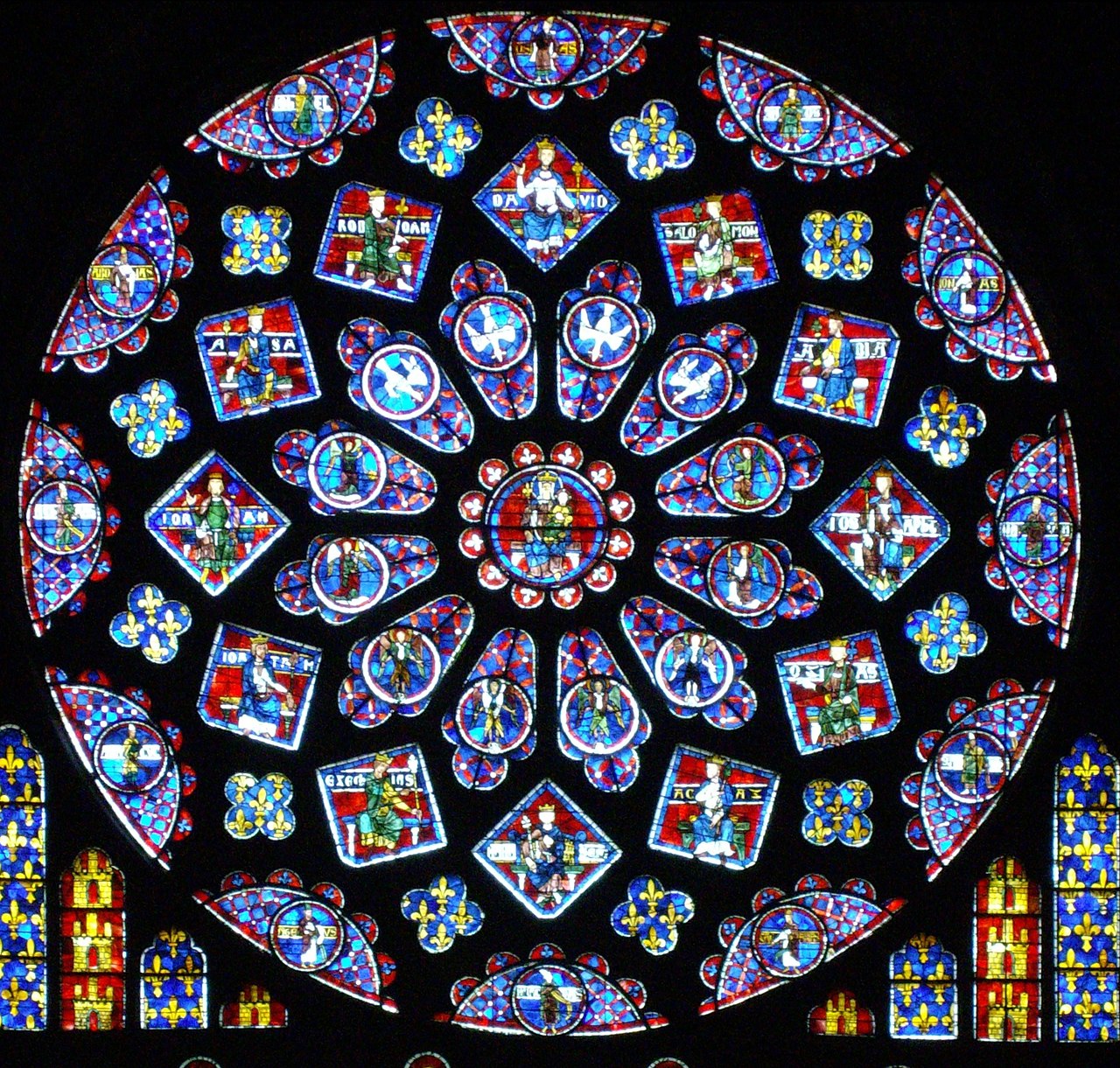【周期性、法則性とアート】
いくつかの「周期」の捉え方について
勉強したので
考えたこと、感じたことと合わせて
アウトプットさせてください。
※※※
まず、最初に来るのが
「明るい、暗い」という概念。
光があれば、闇があり
昼が来れば、夜が来る。
「陰陽」ということ。
これは、「2」区分となる。
「3」は、「開始、定着、変容」
例えば、一つの季節をこの3つに分けて
古代から感じられてきたし
今はちょうど、春から夏への「変容」が
始まったときと見ることができる。
「4」は例えば「火、水、空気、土」などの
「四元素」的考え方。
これらの最小公倍数は「12」である。
バロック時代の占星術では、
これらの組み合わせで各星座の性質を見ており
今で言うところの、星座固有の性格付けは
まだ、概念として成立していなかった。
そして「13」という数字は
「12」のサイクルから飛び出てしまうものとして
「未知の世界に踏み込む」ことから
「死」に通じる数であった。
それは決して悲観的な意味ばかりではなく
むしろ、古いものを終わらせた
新しい始まりであるともされた。
自然現象の一部だったのだろう。
※※※
「5」は一例を取ると
人体を分析するときになど使われたそうで
最小公倍数を取ると「60」になる。
馴染みのあるところでは
「還暦で一周り」ということ。
「7」は文明を分析すると出てくるそうで
私が馴染みあるところで見ていくと
古典占星術は土星以降の惑星がないので
「月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星」
この7惑星で分析される。
最小公倍数は「420」となる。
その数のパターンが存在し
「421」からスタートに戻る。
※※※
そして、一例だけれど
今から60年前は1965年で
今は、当時なかったものがあり、
あったものが、今はない。
周期性を当てはめるにしても
一旦、抽象化して
普遍的なものを見出すことが大切になる。
そして、そのままでは人に伝わらないので
そこからまた、
具体化しなければいけない。
そのプロセスが難しく
個性や各自ものの見方が問われる。
とても、クリエーティブで
アーティスティックだと思った。
※※※
今から420年前だと
1605年になる。